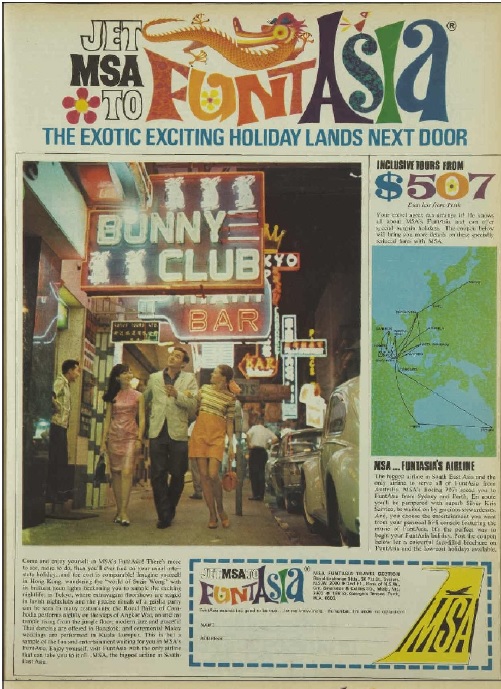Japan will finally re-open its doors to unrestricted travelers in October 2022, over 2 1/2 years since imposing strict entry requirements (especially on foreigners) due to the COVID-19 pandemic. With the yen at its weakest against most major currencies since the early 1990s (and effectively even weaker still in real terms as the yen of the early 1990s carried far greater purchasing power than the yen of the 2020s), tourists are predicted to flock back into Japan. Japan is one of the world’s great tourist destinations and it is Kangaeroo’s belief that the hospitality of many Japanese people show toward…
-
-
All the very best for Christmas 2019! Have a wonderful festive season and take care. May all your Christmases be Chrissie. An Aussie Chrissie Related posts: Dino Might! Tour de Kagoshima-Kyoto Day -1A: Tama Hills to Haneda San-poses! Plastic Roos and Fuji Views Powered by YARPP.
-
Wet season sunrises over Cairns in Australia’s Far North Queensland. オーストラリア北部にあるクィーンズランド州の北部都市であるケアンズにおける雨期日の出。 Related posts: Big Captain Cookが只今売り出し中 米TV局:豪の不思議な怪人の存在確認 ビッグ・アワビが豪メルボルン市の誇り バナナを曲げる人々 People who Bend Bananas Powered by YARPP.
-
オーストラリアの不思議なキッチュオな町おこしオブジェ「Big Things」のひとつである重さ10トンに高さ約4メートルのBig Mangoが今週一旦盗まれたり、見つけられたりして、これに関連して最終的にさまざまな出来事がチキンチェーン店のPRスタントであったことが26日付で分かった。 Big Mangoは、豪北部クィーンズランド州にある同国マンゴ生産一ボエンという町に2002年に地域名物を称えるうえに観光を促進するために設置された。 設置してから2007年にヒュー・ジャックマンとニコール・キッドマン主演「オーストラリア」のロケ地となった期間を除けば同町が平凡な田舎町としてやってきたが、今週24日となったいきなり有名な町象徴ひとつであるBig Mangoの姿が消えていた。 同日、監視カメラが撮影した映像では同オブジェをクレーンが運んでる場面が映られている、という発表があった。 また、翌日、同町内にシートに囲まれている巨大マンゴが見つけられた。 そして、見つかったと同時に米国ファストフードチェーンであるナンドーズが「ボエンの方々に感謝しています。少しの間あなたたちのマンゴをお借りしております。ちゃんと戻すととも理由などを説明いたします」と豪法人ウェブサイトで声明文を出した。 熱帯雨林地の美味しい宝物のBig Mango Big Thingsクイーンズランド州編 Where the Cluck is the Bowen Big Mango? Big Mango tourist attraction stolen from Bowen has been found ‘Stolen’ big mango revealed as a hoax by Nando’s Related posts: 熱帯雨林地の美味しい宝物のBig Mango Tjukurrpa, Terra Australis, New Zealand, EendrachtslandそしてAustraliaへ Big Thingsクイーンズランド州編 Australia Day賛否両論 Powered by YARPP.
-
世界レベルで見ればオーストラリアが高い山がないが、東海岸の数千キロに渡りグレートディバイディング山脈という山脈があり、その一部がとっても不思議な山村が所在するスノウィー山脈もある。 昔オーストラリアで最も標高高い不思議な四つ小さな山村があったが、いずれも比較的に高い山に所在していたにも関わらずいずれも今水沈まれている。 「ええ?高い標高山村が下方向に流れるはずの水に沈まれる訳がない」と一瞬思ったらおかしくないが、原因は日本でもよく見る現象だ、、、ダムづくり。 ジンダバイン、タルビンゴ、タランガッタとアダミナビという山村が水力発電所建設計画だったスノウィー山脈水力発電所計画で沈没され、今同名の各村が元の場所とかなり離れている所にある。日本のような山が多い国ではちっとも珍しくない話だが、山が低くて割と平野が中心となっているオーストラリアでは極めて珍しい話だった。今では干ばつがあれば、古い町も再び現れてきたり、スキーの拠点となったりして、観光業に大きく観光業に貢献している。ちなみに、アダミナビには「Big Things」であるBig Troutがある。下記の映画が古いアダミナビの今を見るものだ。 スノウィー山脈水力発電所計画は1949年から1974年の間に続けた。ダム16ヶ所、水力発電所7ヶ所、トンネルやパイプなど225キロメートルに及び、オーストラリア最大土木インフラ計画だった。 同計画の建設にかかわった労働者約7割が移民だった。1950年代まで移民にかなり否定的なオーストラリアが英国植民地化した1788年以降初めて英語圏外の大量移民を受け入れて現在の多文化社会の出発点と呼ばれ、現代オーストラリアにはかり知らないほど大きく影響を与えたプロジェクトだった。 Our Drowned Town from George Evatt on Vimeo. Related posts: No related posts.
-
オーストラリア北部クィーンズランドにロボットな恐竜約150頭を設置する、と豪最も裕福なビジネスマン一人が4月8日発表した。 億万長者クライブ・パーマー氏(59)はオーストラリア有数なお金持ちであり、自身が所有しているパーマークーラムリゾートでは約150頭の中国製ロボット恐竜をリゾート内のあらゆるところに設けると言った。 「ジェフ」と呼ばれているティラノザウルス1頭を含めて同リゾート内ゴルフコースには既に2頭の恐竜があり、いずれも鳴き声など音がだし、動ける。 パーマー氏によるとリゾート内で置く恐竜すべて音を出すようにし、動けるものも作ると言う。 同氏は、昨年あの有名な客船タイタニック号のそっくり版「タイタニックII号」を作成した。 「俺が死ぬまでに持っている金を使わなくちゃ」とコメントした。同氏の全財産が約8億豪ドル(約796億円)とされている。パーマー氏が主に鉱業と纏わっている。 Clive Palmer unveils plans for life-size dinosaur park (SBS World News Australia) Related posts: 豪出身元祖「クール・ジャパン」支持者が訃報報道を否定 How do you say Skivvy in Japanese? 和風Wiggles 海で下水を流すことに抗議するために制作されたBig Poo 豪史上最低映画から俄ヒットへ Powered by YARPP.
-
イギリスが刑務植民地した1788年以降オーストラリアの存在に大きく関わって、壮大な貢献をしてきた羊。 羊毛でも羊肉でも、そして羊製品などが19世紀初代から現在に渡ってオーストラリアにとって重要な輸出物であり、国内では雇用や商売にかかせない存在だ。 人間一人に対して10匹以上もいる羊がオーストラリアがこの動物をどんなに頼るのかを示すだろう。 だとしたら、もう一つオーストラリアの象徴である形式で称えてもいいだろう? もちろん、羊関係が「Big Things」の仲間に入っている。 実は、同じものを何回も祝っている場合もある。 たとえ、Big Merinoだ。 ニューサウスウェールズ州にあるゴールバーン市が地方都市であり、羊牧場などと歴史が長い。 オーストラリア初内陸都市とも言われているこのゴールバーン市。 メルボルンとシドニーを繋がるヒューム・ハイウェイに位置している。 同市の観光名所となっているBig Merinoがそこに置かれている。 恐らくオーストラリアの数多くある「Big Things」の中の有名なオブジェ一つと思う。 ここではお店やお土産屋などがある。 もう一つのBig Merinoもある。 これがクイーンズランド州のブラッコールという小さな町にある。 ブラッコールという町も同町のBig Merinoのいずれもゴールバーンに負けるがオージー英語ではこの小さな町が重要な役割を果たしている。 オーシー英語では、Beyond the black stump(黒い<木などの>株の彼方という意味)という表現がある。「はるかの奥地」を示す表現だ。 そして、元々の黒い株がこのブラッコールにあったという。(他の町にも同じことを言っている箇所が多数あるけどね、、、)。 ちなみに、Big Merinoのメリノが羊の種類であり、オーストラリアの羊産業で最も関係した種類だ。 ふたつのBig Merinoがあると同じように二つのBig Ramもある。 (ところで、ラム<ram>が「雄羊」という意味、ラム<lamb>(子羊)じゃない。) まず、南オーストラリア州にあるカルーンダ町にBig Ramがある。 これが同地域が羊毛及び羊肉が盛んだから羊を称えようとして作られた「Big Things」だそう。 高さ2メートル位なので、それほどビッグではないよね。 間違いなくデカイRamは西オーストラリア州のBig Ramだ。 これがウェジンという町にあり、考えRooが以前に取り上げている。 また、ラム(雄羊)だけではない。 今回こそラム(子羊)を称える「Big Things」がある。 ニューサウスウェールズ州に一旦戻って、ガイラという町にたどり着く。 ここには子羊だけでなくじゃが芋を称える「Big Things」がある。 ガイラのBig Lambは子羊像であるが、その可愛いな子羊がじゃが芋の上に座っているような感じとなっている。 この地域は、じゃが芋も名産物だそうだ。 そして、それだけじゃない。 羊より羊からとった羊毛もちゃんと「Big Things」に入る。 これがビクトリア州に羊毛生産地として有名なハミルトンではBig Wool Balesがある。 このオブジェが羊毛の袋をでかくしたものだ。 羊毛袋をしているビルは実際にお土産屋とカフェだ。 * これが「Big Things」シリーズ最後となります。 Related posts: 豪で発売するラム肉バーガーこそがオージー味であり、日本マクドナルドが日本消費者に不誠実 このデカさなら羊たちは沈黙する訳! There’s Something Fishy About豪州の魚介類Big Things! Big PeopleがなければBig Thingsが揃わない Powered by YARPP.
-
本物の膨大な3mミミズを称える250mのGiant Worm 煙の出方が間違っているBig Smoke ビッグ・アワビが豪メルボルン市の誇り 野生コアラ公園を見守るBig Koala 「強盗殺人」なのにBig Thingsを含めて豪がNed Kellyを称える理由は何だ? 芸術が盛んな田園町飲屋屋上「偉大死んだ魚」 OECD最低火力発電所周辺にぴったりのBig Cigar モー、、十分か?牛関係のBig Thingsでもオーストラリアに盛ん 世界中に高く評価されている豪ワインを称えるBig Things Big Thingsと妖精ペンギンが溢れる小さな島 There’s Something Fishy About豪州の魚介類Big Things! She’ll be Apples! NYがどうでもいいよ!豪全国各地にあるBig Appleがあるぞ! Big PeopleがなければBig Thingsが揃わない Big Watermelon: スーパーサイズすいかが大型八百屋の看板だ 色々な意味で象徴的な豪の「羊風」Big Things Related posts: OECD最低火力発電所周辺にぴったりのBig Cigar 豪で発売するラム肉バーガーこそがオージー味であり、日本マクドナルドが日本消費者に不誠実 このデカさなら羊たちは沈黙する訳! 煙の出方が間違っているBig Smoke Powered by YARPP.
-
元祖Big Bananaが豪のBig Things原点だ 豪首都の(ちょっとがっかりする、、、)巨大キノコ Big Thingsのはずなのに遥かに本物より小さいのBig Ayers Rock それってアリなの?アウトバック都市の巨大オブジェがアリである 洗濯用たらいと車のマフラーで創られたBig Spiderが田舎町アート原点 どんな蚊取り線香でも効かないBig Mosquito ゴミ捨て置き場前の観光スポットであるBig Bicycle オージー英語のアイコンでもある二つのBig Chook 海で下水を流すことに抗議するために制作されたBig Poo ウィンブルドン選手権優勝にぴったりのBig Tennis Racquet The Big Prawnがオージー版「えび魔よ!」 Big Blue Heelerで豪犬を体験(大犬?)できる田舎町 「果実の都」の象徴となるBig Fruit Bowl 真夏に最適なBig Slurpee(本当は飲めないけど、、、) モー、、十分か?牛関係のBig Thingsでもオーストラリアに盛ん 世界中に高く評価されている豪ワインを称えるBig Things 砂漠の真ん中の大きなBig Park Bench 豪の実力以上のものに挑む精神を表示するBig Guitar群れ There’s Something Fishy About豪州の魚介類Big Things! ‘Must See’よりVitamin Cが相当する豪州の各Big Orange Big PeopleがなければBig Thingsが揃わない でかいボウルズが元気な豪老人の原動力だ! 色々な意味で象徴的な豪の「羊風」Big Things Related posts: Big Thingsのはずなのに遥かに本物より小さいのBig Ayers Rock オージー英語のアイコンでもある二つのBig Chook Striking a Light for Strine 「豪」にいれば「豪語」に従えって? ゴミ捨て置き場前の観光スポットであるBig Bicycle Powered by YARPP.
-
Big PineappleがDaggy文化のキッチュ・キングかも、、、 豪で最も雨が降る町は巨大ゴールデン・ゴムブーツ賞を(勝手に)受賞 恐竜だったことを思わせる豪巨鳥を称えるBig Cassowary 魚、ワニをはじめクィーンズランド北部の様々なBig Things Big Bundy、豪州社会に良い悪い役割を果たしたラム酒を称える Big Captain Cookが只今売り出し中 The Big Redback: 豪文化象徴である「便座の背赤グモ」のBig Things版 熱帯雨林地の美味しい宝物のBig Mango 人気動物園の相乗効果でBig Mowerの展開動力 モー、、十分か?牛関係のBig Thingsでもオーストラリアに盛ん 世界中に高く評価されている豪ワインを称えるBig Things 豪の実力以上のものに挑む精神を表示するBig Guitar群れ There’s Something Fishy About豪州の魚介類Big Things! ‘Must See’よりVitamin Cが相当する豪州の各Big Orange 元々祭りの山車だった違う州2つのBig Pelicans 宝を含める豪のBig Thingsの宝箱地域 豪国民食であるミートパイを称えるBig Pie 色々な意味で象徴的な豪の「羊風」Big Things Related posts: 熱帯雨林地の美味しい宝物のBig Mango 恐竜だったことを思わせる豪巨鳥を称えるBig Cassowary 洗濯用たらいと車のマフラーで創られたBig Spiderが田舎町アート原点 Big Captain Cookが只今売り出し中 Powered by YARPP.